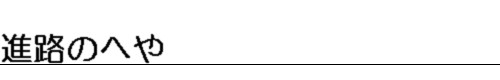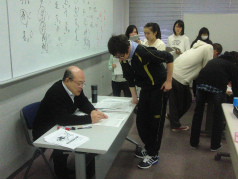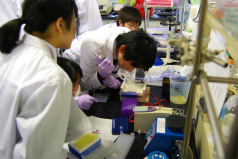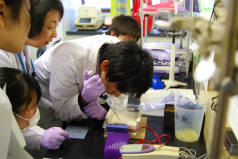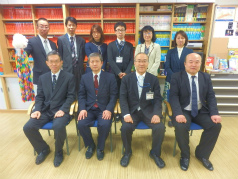4月6日(月)、京都・文化体験企画を高2日本史選択者有志により開催しました。
Academic Summerの一貫とはいうものの、時期は春休みということでイレギュラーではありますが、日本文化を育んだ京の都の春・桜を体感することができました。
今回は、学校の授業だけではなかなか生徒が実感することのできない“文化”に興味を持ってもらうことを目指し、“文化を体験する”“文化に触れる”ということを目的としています。
まず、京都五条にある風俗博物館で、寝殿造の構造や平安時代の年中行事などを学びました。


今回は曲水の宴や元服の式の様子などが再現されていました。
次に、実際に袿や狩衣の着付けを教えて頂き、生徒達も実際に古代の衣装を互いに着付けてみていました。
本の中の絵で見るだけであった装束がどのようなものなのか、古代の人々はどのように考えて装束を整えていたのか、学ぶことができ、生徒達も非常に興味深かったようです。
最後に装束の畳み方まできちんと教えて頂きました。


その横では、平安時代の遊びである偏つぎや双六などに挑戦する生徒たちもいました。

続いて同志社大学に伺い、同志社歴史資料館の若林准教授より同志社周辺の史跡について講義して頂きました。


出土した地層の見分け方や出土遺物から伺える調査結果などを説明して頂いた後、実際に同志社大学の敷地内を発掘調査により発見された相国寺の礎石や花の御所の遺構などを案内して下さいました。
同志社大学からは徒歩で京都御苑を北から南まで突っ切り、公家町や御所の大きさを自分達の目で確かめる時間としました。
現在に残る公家屋敷である冷泉家を見た後、公家町の広がっていた京都御苑へ。
授業で扱った蛤御門も実際に目にすることができ、生徒たちは感激したようです。
蛤御門の変で門に付いた銃弾の跡を熱心に見ていました。

閑院宮家や九条家跡を見て御苑を出る頃にはへとへとになっていた生徒達ですが、御所や公家町の広大さを身に沁みて感じたようです。
この後は東山の体験工房EN家で、香道体験をさせて頂きました。
香道は日本文化の中でも重要な位置を占め、古典を読む際にも必要とされる知識でありながら、現在では華道や茶道のようになかなか触れる機会もなく生徒たちには理解が難しいものです。
その香道に僅かながらでも興味を持つきっかけとなれば、と今回企画をしました。
今回は生徒になじみやすい、匂袋作りという形にさせて頂きました。


香に使う材料の説明を受けた後、実際に竜脳や白檀、大茴香の香りを聞かせて頂き、自分たちで匂袋に入れる香を調合してゆきます。


袋は西陣織・縮緬の布から自分たちの好きな模様を選んでいます。

できあがりです!
やはり生徒たちそれぞれに調香に癖があり、お互いにこの香は爽やかな香りがする、とか甘い香りがする、とか評価しあっていました。
嗅覚に訴える形でそれぞれの個性が出せるところが、香道の魅力であり、面白さですね。
最後に下鴨神社へ。
下鴨神社は葵祭を執り行う社であり、京の地下に存在する豊かな水脈を実感することができる場であもあります。
先ほどまで賑やかな街中にいたというのに、一歩踏み込めば独特の静謐さと水の気配がする下鴨神社、そして糺の森に、生徒たちは何か厳粛な気持ちになったようでした。
そして、糺の森の中の川や森の美しさに見ほれて、あちこちにカメラを向けていました。
都会育ちの生徒たちには、これだけでも良い体験になったのではないかな、と思える良い表情をしていました。

葵祭の行われる社や古代の祭祀の史跡を廻り、ちょうど式年遷宮にあたっている下鴨神社の様子も目の当たりにすることができました。
1日で盛りだくさんの日程でしたが、全員元気に行程をこなすことができ、無事帰途に就きました。