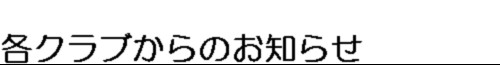環境大使 きずきの森保全活動
11月2日(日)、環境大使と担当教員とできずきの森へ行ってきました。定期的に外来種ハリエンジュの駆除作業と植樹木のお世話を行っていますが、今回の活動では、きずな会主催の自然観察会「秋のキノコ」に参加しました。まず拠点地で講師の先生のお話を聞きます。第一声言われたのは「キノコを食べる、食べないの観点で判断することはやめましょう」ということ。キノコは1万3千年前のチリ遺跡でも発見されており、5千3百年前のアイスマンの持ち物にサルノコシカケがあったことからも人類と長い歴史を共有してきたことがわかります。3千種(5~6千種あると推定されている)のうち、食べられるキノコは百種と言われているが、少しでも症例が報告されたキノコは毒キノコに分類されてしまうので、その境界線もあいまいであるということでした。キノコ採りの注意事項を聞いて早速出発しました。途中雨に降られましたが、たくさんのキノコに出会うことができ、専門家の先生の解説も伺って、有意義な時間を過ごすことができました。大使のみなさんお疲れ様でした。次回の作業もがんばりましょう。
*今回出会ったキノコ*ホコリタケ(雨粒が落ちると胞子が飛ぶ。白い間は食べられる) アシボソノボリリュウ(カサを閉じているのが通常。今回は雨だったので開いていた。似ているキノコで猛毒のものがある) ヘビキノコモドキ(もどきというのに、ヘビキノコはない。カサに筋がある。) ベニタケ(この仲間は30種類くらいある。カブトムシの匂いがするものも。ドクベニタケは毒とついているほど毒はない。腹痛程度だが食べてもおいしくない。) サルノコシカケ(これがついている木は体力のなくなっている木。漢方として有名。) カワラタケ(実はサルノコシカケより漢方の効用があると言われている。) オオホウライタケ(ひだがあってシワシワ。色は濃いものも薄い物もあるので色だけでは判別不可能。) シロヒメホウキタケ(別名ソウメンタケ。白くて素麺のようなので。) ホウキタケ(似た形で根が太くて先端がとがっているものは食べられるものがおおい。箒のように根からバラバラになっているものは食べてはいけないというのが原則。) コガネタケ(食べるとホコリくさい。道の行き止まりなどによく生えている。) キシメジ(シメジは下がふくらんでいるのが特徴。土地を占めるくらいまでふえるのでシメジという名がついたとも。) ウラベニガサ(裏がほんのりピンク。こういう特徴のキノコは食べられない。) エリマキクリタケ(株ででてくるキノコ。ナラタケに似ている。) イグチ(ひだはなく、中がスポンジ様になっている。スポンジ状の部分には虫がはいっていることが多い。) チシオタケ(傷つけると赤い液が出るのでこの名がついた。) ツキヨタケ(夜光る。) アシナガタケ・モミタケ・ウマノケダケ・ヌメリイグチ・チャツムタケ・ヒイロタケ・クチベニタケ


講師の先生の説明を聞きながらメモ 足元をみながらキノコ探し
今巷で話題になっている「カエンダケ」についても特徴などをお話しいただきました。


説明を聞く こちらはカワラタケ クリタケを触る・・不思議な感触


見つけた!の声で集合 大きなナメクジでした。。
きずきの森のキノコたち
















色々なキノコ。たくさんとれました。

ひとつずつ解説をしていただきました。
青変・黒変など、採ってから色の変わるキノコがあることも知りました。


本日の一番人気は・・・不思議な感触の「ホコリタケ」! みんなで触っていました。
以下大使感想
・楽しかった! キノコのことがよくわかった。
・キノコ採り楽しかった。特にクリダケが良かった。触りごごちに驚いた。
・森の散策途中に雨が降ってきて大変だった。
・枯れている木は菌に対する抵抗力がないのでキノコが生えやすいと知った。
・ヒイラギナンテンを教えてもらった。これも外来種だった。
・菌輪というキノコの生え方を教えてもらった。
・上に伸びていくからこの名前がついた「ノボリリュウ」はゴムみたいな外見だった。
・ハンノキにしか卵を産み付けないミドリシジミの卵を見れた。
・ヤツデの葉っぱを数えた。植物の葉の数は奇数だと知った。
・裏が赤いキノコは食べない方が良い。黒いキノコには毒があることが多い。などがわかった。
・きのこをたくさんとった。食べられないキノコの方が多かった。
・山中で良くみたらたくさんのキノコが生えていた。
・種類が明らかなキノコでも、食べられるか食べられないかわからないキノコの方が多いと知った。
・雨がたいへんだった。とにかく怪しいキノコには手を出すな!ということがわかった。