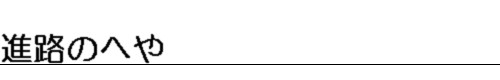one day college 感想文(17)-京都大学-


京都大学 総合人間学部
-講座紹介-
英語から見えることばの不思議
英語を学習するとき、単語や熟語の意味を覚えたり、文法や構文を覚えたりする中で、「なぜこの語はこんな意味になるのだろう?」「この構文とよく似たあの構文とでは何が違うのだろう?」「日本語と違って、英語ではなぜこういう表現になるのだろう?」と思ったことがあるかも知れません。普段はなかなか向き合うことのできないそのような疑問に、言語学はどのような答えを与えることができるでしょうか。中学校・高校で学ぶ英語を題材に、私たちが使うことばの不思議さやおもしろさを示していきたいと思います。
-生徒感想文-
・これまでは、英語で異なる言い方をしていても、日本語に訳すと同じだから、それらはすべて同じ意味だと思っていましたが、違う言い方をするということは、主語の違いがあったり、その人それぞれのものの見方が違うということがわかりました。また、受け身にするのにも、そのような理由があることも知りませんでした。文のひとつひとつにこれほどの違いがあることに驚きました。これから、これらを生かして英語を使っていくようにしたいです。(高1女子)
・能動態から受動態に変えるときや、第4文型から第3文型に変えるときに使えない文があることを知りました。受け身になるためには理由が必要であることも分かりました。これから英語を学ぶときには、意味を一つ一つ考えながら、問題などを見ていきたいと思いました。また、疑問に思ったら、その疑問を大切にしていきたいです。(高1女子)
・言語学がとても幅広いジャンルで構成されていることにとても衝撃を受けました。言葉が日常生活の周りにあふれていて、お互いに深いつながりを持っていて密接に関係していることが特に印象に残っています。大学に行けば、今、疑問に思うことをとことん勉強したり、研究したりできるのがとてもよいと思いました。(高1女子)
・自分が注目するものに焦点をおいて、それをできるだけ自分のとらえたものに近い形で表現しようとしていることを調べる学問は面白いなと思いました。自分の見方に近い表現をしても、それを伝えた相手にはまた違うとらえ方をされる可能性がある。すべての人が、共通の認識を持つことは難しいと思いました。文法では、能動文、受け身文にすべての文ができるわけではないというのも知りました。そのものにある状況や意味に適した表現が必要であると思いました。(高2女子)
・今回の講義を受けて、認知言語学とは、心理学と言語学の融合のような学問だと分かりました。英語の構文にはさまざまな意味があることもとも分かました。受動態と能動態の使い分けや、前置詞構文の使い方、第3構文型、第4文型の使い分けの方法が分かり、とても楽しかったです。(高2女子)
・英語圏では「南極大陸」はペンギンは所有できないという考えらしい。英語圏での所有とは「人が」所有するものらしいので、「人」でない南極大陸はペンギンを所有できないことになる。日本人の私からすると、南極大陸の自然環境の恩恵を受けてペンギンは生かされているので、「南極大陸>ペンギン」であり、南極大陸がペンギンを所有しているといえるんじゃないかと思った。西洋と日本の自然観の違いを見た気がした。(高3女子)