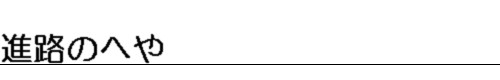企業最前線! 職業人インタビュー(6)


小関 智弘 氏
こせき・ともひろ●1933年,東京生まれ。都立大学付属工業高校卒業後,大田区内の町工場に就職。ベテラン旋盤工として働くかたわら,作家としても活躍。61年,『ファンキー・ジャズ デモ』で文壇デビュー。『錆色の町』『地の息』が直木賞候補,『羽田浦地図』『祀る町』が芥川賞候補に選ばれる。著書に『春は鉄までが匂った』(ちくま文庫)『職人学』(講談社)『鉄の花―町工場短編小説集』(小学館)『働くことは生きること』(講談社現代新書)『ものづくりの時代―町工場の挑戦』(日本放送出版協会)『町工場巡礼の旅』(現代書館)『大森界隈職人往来』(岩波現代文庫)『仕事が人をつくる』(岩波新書)『おんなたちの町工場』(ちくま文庫)『粋な旋盤工』(岩波現代文庫)『鉄を削る』(ちくま文庫)『ものづくりに生きる』(岩波ジュニア新書)などがある。
--------------------------------------------------------------------
※インタビュー:2004年3月19日
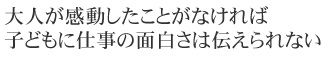
不況になると町工場にしわ寄せが行って,どんどん倒産もしくは転廃業してその数は減る一方です。日本の町工場のメッカといわれる大田区には,92年の頃には8000軒の中小企業がありましたが,今では6000軒。実は,この問題は不景気になる前から指摘されていました。廃業か倒産の理由のほとんどは後継者不足なんです。バブルの時は「3K労働」などと言われて,若者が現場を嫌うようになってしまった。そのうち不況になると設備が更新できず老朽化する。それを後継者がいないから技能でカバーできない。ますます仕事が入らず,若い人を採用するゆとりができない。そんな先細りの悪循環です。「町工場は,景気がいいと人をさらわれ,景気が悪いと仕事をさらわれる」と言われていました。
そんな危機感もあって,わたしは町工場の人たちがどれだけ豊かな人生を過ごしてきたかを書き続けてきました。デジタル指向の急激な進展もあって,労働の中味が変質し,物事の背景が見えなくなっているんじゃないでしょうか。効率化のためのマニュアル一辺倒で,言われた通りのことだけしていればいいと。むしろ余計なことは無駄だからするなと怒られる。自分がやることの前後左右に何があるのか,自分の位置を把握することをしなくなっているんです。人間はさぼるし不平を言うから,なるべく排除して機械化しようと。これは,いわば人間不信のシステムではないでしょうか。
大企業の製造現場などで火災などの事故が起きているのも,その反動ではないか,と言われもしました。技能の承継は多くの企業で問題にされ,マイスター制度などを取り入れて技能承継に努めている企業が増えました。働くとは,にんべんに動くと書く。にんべんを取っ払って動くのはやはりダメだ,と反省して変わってきているんじゃないでしょうか。大量生産・大量消費の社会が行き詰まって,付加価値のある多品種少量生産のために人間の能力が見直されているからでしょう。このことはゆとりのある大手企業から始まりましたが,中小企業でも,いいものづくりをしているところには若い人が入って継いでいます。