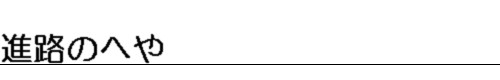今だから考える大学入試(1)

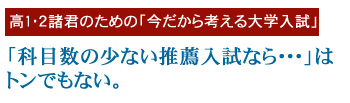
卓球の福原愛選手と、早実の斎藤佑樹投手が早稲田大で同級生になる、と話題になったのは記憶に新しい。福原選手が受験した入試は、オリンピック級の活躍が見込まれるアスリートを対象とした、早稲田人・スポーツ科学の 「トップアスリート人誠」(AO方式)である。早稲田大・スポーツ科学の偏差値は60を超えている。日本を離れ、「中国スーパーリーグ」 で活躍していた福原選手にとって、一般人試は高いハードルであったはずだ。しかし、推薦入試やAO入試は、そこまでの学力は求めていない。ペーパーテストを重視する一般人試に対し、推薦入試やAO入試は、クラブやボランティアなどの活動歴などを問う人試だからだ。
今や、推薦入試とAO入試を合わせると、大学の全入学者の約42%を占める。そのうち、推薦入試に限ると、35.6%にもなる。当然、推薦入試を実施している大学数も多い。早稲田大はもちろん、慶應義塾大、上智大、明治大、同志社大、立命館大、関西大など、推薦入試を行っていないブランド大学は皆無と言える。人気が高い医学部も、埼玉医科大や東京女子医科大などが実施している。
また、国立大でも後期日程を廃止した定員の一部を、推薦入試やAO入試に回す大学が増えている。07年は東京工業大・1類や岡山大・広島大・総合科、薬などでAO入試を導入する。地方の医師不足を解消するために、弘前大や山口大など、医学部の地域推薦枠を設ける大学も増えている。難関国立大で推薦入試もしくはAO入試を実施していないのは、東大や京大など、一部の大学に限られる状況だ。
推薦入試のメリットは、学力が評定平均値で担保されるため、原則として学科試験が課されないことにある。大学個別の試験は思考力や論理力を見る、小論文や面接の場合が多い。最近は、独自の試験で学力を見たい、というこから、関西の大学を中心に学力試験を重視する推薦入試が増えている。しかし、その際も地歴や理科は課されないことが多い。少数科目で受けられる推薦入試の利点を、河合塾教育研究部チーフの神戸悟さんは、こう話す。
「現役生は、英数国といった主要科目に比べると、地歴や理科の勉強が遅れがちになるものです。入試科目数が少ない推薦入試なら、これらの科目の勉強が遅れても、合格できる可能性があります。志望校なら利用すべきでしょう」
もちろん、科目数のハードルは低くとも、難関大の入りやすさに直結しないことは言うまでもない。「有名大学は倍率が高く、優秀な受験生が集まるため、一般人試で合格できる大学より、ワンランク下げなければならない場合も多いようです。本人の将来を考えると非常にもったいないと思います」 そう話すのは、現役生を対象にする市進予備校入試統括室の小林国弘さん。例えば、慶應義塾大・文は、評定平均値が4.3あれば出願できる。しかし、これはあくまでボーダーラインであって、「実際に合格するのは、オール5に近い受験生が大半だろう」 と、多くの受験関係者は話す。難関大が課す小論文や面接は、高度な論理力や思考力を問うものが多く、一筋縄ではいかない。入試形態は異なるが、上位大学の場合、ベースとなる能力は一般入試と変わらない,とも言われている。
そんな難関大の推薦入試について、ベネッセコーポレーション高校事業部・情報本部統括責任者の木野内俊典さんは、こう話す。
「一般人試でも受験を考えている大学なら、受験機会の拡大ととらえて、積極的に利用するべきです。ただし、不合格になってしまった時には即座に頭を切り替えないと、一般人試も失敗してしまう恐れがありますので注意が必要です」
「夏休みを過ぎると、思うように学力が伸びず、推薦で合格して、早く楽になりたがる受験生もいます。しかし、苦しいのは誰も一緒です。一般入試を考えていた受験生には、初志貫徹してほしいと思います」
(サンデー毎日10月15日号より抜粋)