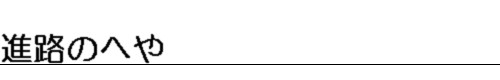企業最前線! 職業人インタビュー(5)

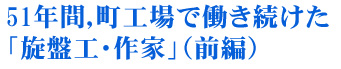
小関 智弘 氏
こせき・ともひろ●1933年,東京生まれ。都立大学付属工業高校卒業後,大田区内の町工場に就職。ベテラン旋盤工として働くかたわら,作家としても活躍。61年,『ファンキー・ジャズ デモ』で文壇デビュー。『錆色の町』『地の息』が直木賞候補,『羽田浦地図』『祀る町』が芥川賞候補に選ばれる。著書に『春は鉄までが匂った』(ちくま文庫)『職人学』(講談社)『鉄の花―町工場短編小説集』(小学館)『働くことは生きること』(講談社現代新書)『ものづくりの時代―町工場の挑戦』(日本放送出版協会)『町工場巡礼の旅』(現代書館)『大森界隈職人往来』(岩波現代文庫)『仕事が人をつくる』(岩波新書)『おんなたちの町工場』(ちくま文庫)『粋な旋盤工』(岩波現代文庫)『鉄を削る』(ちくま文庫)『ものづくりに生きる』(岩波ジュニア新書)などがある。
--------------------------------------------------------------------
※インタビュー:2004年3月19日
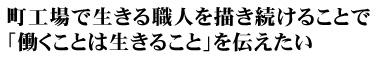
私は,2002年に,51年間続けた旋盤工のキャリアにピリオドを打ちました。会社が工場を貸しに出すことになって,わたしが使っていた旋盤が売りに出されることを機に引退することにしたんです。それ以降はもっぱら本を書いています。
私は中学・高校とずっと同じ文芸部で活動していました。工業高校という名前でしたが,終戦直後の混乱もあって普通科が併設されていました。ついに一度も工業の勉強をしないまま,工業高校を出て旋盤工になったわけです。そこを卒業して初めて仕事に就いたのは終戦の6年後の昭和26年。親父は大学に行かせたいと言ってくれましたが,冬,寝ていると布団に雪が降り積もるような家で,とてもそんな経済状態ではありませんでした。それに,文学を通じてひそかに労働者に憧れていました。しかしながら,ただでさえ就職は容易じゃなかった時代に,高校の時分は政治活動もしていて札つきだったものだから,学校は就職先を紹介してくれなかった。学校は京浜急行の駅のある鮫洲にあり,品川まで4つの駅を求人の張り紙を探して歩いたんです。たった1枚,「旋盤工見習募集,委細面談」という張り紙を見つけました。親父さんのほかに職人が2人の町工場で,すぐ就職することに決めたんです。あらゆる工作機械は旋盤をベースにして作られていたこともあり,花形の旋盤工は肩で風切って歩いていましたね。いまのITエンジニアみたいなものでしょうか。
その後,「渡り職人」としてほうぼうの町工場を移りました。つねに最新の機械に挑戦していたいという思いや,削るものの難易度を上げていかないと職人の腕がなまるという矜持がありましたから。数々のものを削ってきましたが,一番思い出に残るような大仕事は,幅が2メートル,重さが3トンある1つの部品。それをミクロン単位で削るわけで,失敗したらオシャカになってしまう,足が震えるような仕事でした。製品としては,発電機のタービンの羽の試作品は面白かった。ひずみが出ないように仕上げなきゃならないんですが,0.1ミリ間違えたら高級車1台がパーになる,と言われて。しかも,試作品はたいていが急ぎの仕事で,トラックが工場に横付けして待っているんです。そんなプレッシャーもあって,鼻唄歌いながら作業やってても,内心は穏やかじゃありませんでしたがね。
まさに世界最高レベルである日本の技術力を分解していって残る要素に,町工場の職人の技術があったことに間違いはありません。町工場が日本の高度成長,経済発展を支えていたんです。旋盤工の仕事の面白さは,どういう鋼を削るときはどんなバイト(刃)がよいか,そのときの切削条件はどんな値がよいか,といったノウハウの奥の深さとでも言ったらいいでしょうか。鋼に向かって語りかけると,初めて鋼が姿を見せてくれるような境地がありましたね。「キリコ」と呼ぶ,削りくずの形状を見れば,削った旋盤工のウデ,つまりその町工場のレベルがよくわかるんです。それと,渡り歩いた現場のどこも,乏しい設備を知恵で補って,教科書やマニュアルにない使い方を工夫していました。そんな現場力といったものの奥の深さが,まさに仕事の面白さそのものではないかと思います。
ところで私は,作家としても芥川賞や直木賞の候補に選ばれるなどはしましたが,作家だけで生きていくという考えはありませんでした。筆一本で生きていくだけの自覚がなかったんですね。たとえば恋愛ものとか,フィクショナルなものを書けるだけの力もありませんから,とても3人の子どもを養ってはいけないだろうと。また,ちょうどその78年の頃,NC旋盤といってコンピュータで制御する全く新しい機械が登場したんです。それにショックを受けて,マイクロ・エレクトロニクス化がものづくりをどう変えていくか,10年間は現場で見据えてやろう,と思ったんです。その通り,すごい勢いで変わっていきました。いずれにしろ,自分が書きたい題材は現場にあったんです。それで,編集者などからわたしの肩書きを聞かれたときは「旋盤工・(ナカグロ)作家」と答えていました。
著書(*1)に「町工場の旋盤工という労働生活を底荷として,ずっと文章を書いてきた」という一説があるんです。「底荷」とは,船の重心を下げて復元力を増すために船底に積む重量物のこと。ある文芸評論家が,わたしにとっての旋盤工という仕事をそのようなものだと書いてくださった。ですから,専業作家という誘惑に揺られながらも,揺れ戻ることができたのだろうと思っています。この二十数年間に書いた本を並べて見ると,旋盤工として働き続けたからこそ書けた本ばかりです。(後編に続く)
(*1)著書:『働くことは生きること』(講談社現代新書)
『企業最前線!職業人インタビュー』(キャリアガイダンス@メール,リクルート社)より