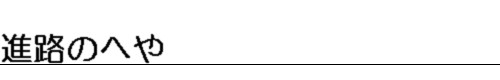国境なき医師団日本会長(黒﨑伸子)のインタビュー記事よりーその1-
 黒﨑伸子さんは、長崎大学医学部を卒業された外科医で、現在、「国境なき医師団」の日本会長です。学研・進学情報誌に、黒﨑さんのインタビュー記事が載っていて、印象深かったところをご紹介します。医師を目指す皆さんは、黒﨑さんの言葉を少し心にとどめておいてほしいと思います。
黒﨑伸子さんは、長崎大学医学部を卒業された外科医で、現在、「国境なき医師団」の日本会長です。学研・進学情報誌に、黒﨑さんのインタビュー記事が載っていて、印象深かったところをご紹介します。医師を目指す皆さんは、黒﨑さんの言葉を少し心にとどめておいてほしいと思います。
先ず、「国境なき医師団(MSF)」は、非政府機関(NGO)であり、日本の場合、民間の寄付で成り立っています。政府や国際的機関からの資金援助を受けると、援助活動の内容や地域が限定されるからだといいます。では、どのような地域で活動されているのかというと、紛争地、感染症流行地、災害地で、災害地がニュースでよく取り上げられるが、実は災害地は年間10%もないらしいです。日本の国境なき医師団が行っているところは、人道的に問題のある地域や他の医者が誰も行かない地域などで、ニーズがあるところを自分たちで探して赴くとのことです。1~2ヶ月だけの人もいれば、1~2年行く人もいるらしいです。MSFは医療スタッフ(医師、看護師、心理療法士、臨床検査技師、薬剤師)が6割で、残りの4割は病院建設や電気・水道の確保、現地の人を採用するアドミニストレーターなどの非医療スタッフだと言うことです。さて、ここで、黒﨑さんからのメッセージで気になったことがあります。それが以下の事です。
「日本では医学部教育が非常に専門化して、すべてを診療できる医師があまりいなくなっています。総合診療院やその人材も増えてきましたが、海外に比べると、日本から送れる人材に限りがあるという問題があります。」
そうなのです。総合医が少ないのです。これは、僻地医療問題にもつながっていると思います。この続きは、次回に。