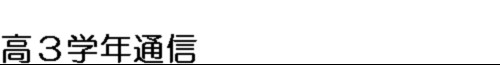学力の向上について⑫
授業には大きく分けて2つのタイプがあります。理科系と文科系のことではありません。それは学問を体系立てて分類したときの区分です。授業方法をタイプに分けると、一つはInput中心の授業、もう一つはOutput中心の授業になると思います。教科・科目によって分けられるのではなく、その授業をおこなっている担当者の考え方や扱っている教材に左右される部分です。
Input型の授業では知識の説明が中心になります。歴史の授業で「群馬県岩宿遺跡で相沢忠洋によって打製石器が見つかった」とか、英語の授業で「使役動詞のmakeは『強制的に~させる』の意味になります」といったことを、教師が一方的に話しているものを指します。Input型の授業では、予習には効果がありません。予習で分かる程度の授業ならば受ける意味はありませんし、分かったと思っている生徒のほとんどが内容を過小評価していて、実はわかっていないのに分かったように誤解していることも多いのです。このタイプの授業では授業内容の把握と復習が重要なポイントになります。
ただし中学生の場合、まったく予習をしないで授業を受けると困る場合もあります。それは前提となる言葉や知識の欠如です。耳から入る情報量が多いので、重要語句の読み方を知らないと、理解度が低下する危険性があります。「そうしようるいのくきのとくちょうはかんじょうにならんだいかんそくとけいせいそうのそんざいです」と聞いたときに「双子葉類の茎の特徴は、環状に並んだ維管束と、形成層の存在です。」と頭の中で直せるかどうかが、理解の分かれ目になります。5分程度のわずかな時間で良いので、教科書や参考書を使ってキーになる重要語句の読み方を調べておくと良いと思います。
Input型の授業を受ける場合に、どのようなノートをつくると効果的でしょうか。これが明日の内容です。