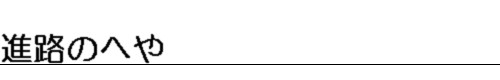目にとまった新聞記事

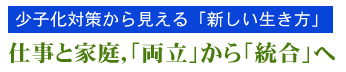
育児経験のない高校生に判れ!という方が無理かもしれません。しかし,少子高齢化の社会で働くのは今の若者。「育児と仕事」はキャリア形成上重要なテーマではないかと思います。
結婚しない人も増える中、育児休業だけに力を注げば不公平感につながる。それよりいろんなニーズで『休める』仕組みを作り、それが職場にとってもメリットになるという理解を広げることが、これからの日本には重要ではないか」 内閣府の「少子化と男女共同参画に関する専門調査会」委員などを務める岩男寿美子・慶応大名誉教授が、サントリー文化財団が開催するフォーラム講師に招かれた際の発言だ。
この日の主題は「少子化と父親の育児休業」。女性の育休取得が7割以上なのに、男性では0.56%に過ぎない(04年度、厚生労働省調べ)。一方、岩男さんが未就学児童を持つ首都圏の男性会社員千人を調べると、育休を「検討したが取らなかった」 「相談したが取れなかった」の合計が12%を超えた。「実際に取った」 (1.3%)もいて、「取る気がない」男性ばかりではないのである。
そこで岩男さんは、育児を経験した男性がそろって挙げた「効率的に仕事するようになった」や「意思疎通がうまくなった」などの変化をアピールしたいという。個人の能力向上は職場にとってもプラス。そんな理解が定着すれば、育休に「抵抗がない」を超えて「積極的に取る」発想につながると岩男さんは考える。「仕事と家庭生活を、エネルギーや時間を配分して『両立』しようと思うから限界がある。両方を統合し、どちらも今まで以上に充実する新しい生き方を探る時代でしょう」
「理解」が浸透していない現状で「何も長期間完全に休むことはない」。週に何回か半日休むだけでも育児は経験できる。父親の関与で、心ならずも「育児に専念」する母親が短時間でも解放される効果も大きい。
「そして、未知の経験機会は育児に限らない。休みと仕事の相乗効果を生かした『柔軟な働き方』が実現すれば、日本社会は大きく変わるはず」
少子化対策から見えてきたそんな「生き方」の再構築が、うつ病や虐待の多発に悩む現代日本の閉塞を打ち破るのかもしれない。
朝日新聞11月2日夕刊「単眼・複眼」から