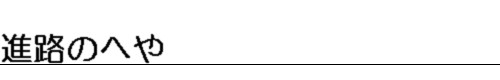家庭学習の環境 4
私たちの周りには、普通に生活しているだけでも、色んな音が鳴っています。あらためて身の回りの音を意識して聞いてみると、何と雑音の多い中に居てるのかと気づくと思います。そして、国によって、音に対しての表現が違ったりします。私達は、虫の“声”と言いますが、他国では“ノイズ(騒音)”と表現するようです。確かに、秋の虫の声は穏やかな気持ちになれますが、夏の蝉の声は、集団になると“ノイズ”と化しています。おかげで我が家のテレビの音量は、冬に比べて夏の方が、かなり大きくしないと聞こえないほどです。
このように、音というのは、時と場合によって、また人によって感じ方が違ってきますので、音楽を聴きながらの勉強が、いいのか悪いのかは、一般論としても定義しにくいのです。
私の場合、ある程度の絶対音感を持っているため、音楽を聴きながら勉強をするなんて、絶対に無理なんです。たとえ、それがモーツァルトであっても、私には美しいハーモニーと感じる前に、ドレミの嵐が降ってくるし、歌にいたっては、ピッチ(音の微妙な高さ)が気になったりと、かえって混乱してしまいます。
医学的には、右脳と左脳の働きの関係から、勉強している間は、主に左脳が活躍し、音楽を聴いているときは、主に右脳が活発になると言われています。だから、これらを同時に行うと、脳全体が活動していることになり、疲れも多くなるから、勉強している間は音楽を流さず、キリが付いたころで、左脳を休ませるために音楽を聴き、右脳に血液を循環させることで、能率を上げることができるそうです。
ところが、音楽の力を借りることで、静かな環境を作ることも考えられます。家のある場所が、繁華街の中だったり、家族の中で、あるいはご近所で、熱心に楽器の練習に励んでいる人がいてても、そう簡単にやめてもらう訳にもいきません。そんな時は、自分の好きな音楽や、自然の音(水の流れる音や鳥のさえずり等)を、小さな音でかけることで、マスキング効果を期待できるのではないでしょうか。ただし、聴き入ってしまっては、何の効果も期待できませんが…。
いかがでしょうか。音に対して、自分はどのような感覚を持っているのかを探ってみた上で、自分なりの音楽との付き合い方を考えてみてください。