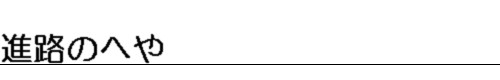入試「小論文」は易しいか
以下の、神戸大学の2011年度の後期日程文学部の小論文問題の設問を見てください。題者が受験生に求めている「小論文力」がよく示されています。あなたが受験生ならどういう視点から問題に取り組みますか。
| 次のA Bの文章は、ともに文学作品の翻訳について述べたものです。(岩波書店編集部編「翻訳家の仕事」岩波書店2006年)。(B5、6ページ) A 多和田葉子「ある翻訳家への手紙」 B 丘沢静也「飼い犬のしあわせ」 | |
| 問1 | 文章Aの傍線部に「基本的には、あらゆる翻訳は「誤訳」であり、あらゆる読解は「誤読」かもしれない」とありますが、どうしてこのような判断が可能なので しょうか、三〇〇字以内で説明しなさい。(配点50点) |
| 問2 | 文章Bの傍線部に「読みやすくて、なめらかな日本語は、文学の翻訳の必要条 件ではない」とありますが、どういうことですか。筆者の意図を三〇〇字以内で説 明しなさい。(配点50点) |
| 問3 | 文学作品の翻訳に対してとるべき態度として、あなた自身はAの立場とBの立場のどちらがよりふさわしいと考えますか。それぞれの立場を比較検討しながら、 八〇〇字以内で自由に論じなさい。(配点一〇〇点) |
この設問を見てすぐに分かることは、課題文を読んでただ単にあなたの翻訳についての「感想」を一四〇〇字求めているのではないということですね。
Aの文章、Bの文章の正確な読みとりがまず問1、2で要求されています。しかも、「逆説」を正しく読み取れるかどうかを問うています。「逆説」ってなんだ、などと言っていては話になりません。
また、問3は「自由に論じなさい」とあります。あなたはこの「自由」の意味がわかりますか。条件があります。「それぞれの立場を比較検討しながら」です。つまり、ここでもAとBとの意見の異同、差異について正しく読み取れているかどうかを出題者は試しているわけです。その上であなたに「自由に」というのです。「自由に」書けますか。この問題には「完全な自由」はありません。
「小論文」は、一般入試と違って、自分の意見や感想を「自由に」書く「作文」だから、易しいなどと考えているとしたらそれは大間違いです。むしろ、文章を要約する理解力、読解力、それを適切に表す表現力が要求され、それを踏まえてようやく自分自身の考えをまとめる思考力など総合力が試されるのです。
考えてみると、問題文は難解でも、一般入試の客観テストは読解力だけ、記述テストは読解力と表現力だけで勝負できるのだから「小論文」よりずっと易しいともいえるのです。
進路 AO小論文担当より