第3回小論文講座
2月初旬から始めた小論文講座の第3回目の様子です。

要約練習も終わり,いよいよ小論文という回になって,大流行の風邪(インフルエンザ)のためか欠席者が多く見られました。しかし,参加者は頑張っていました!!自分の好きなことだけを書くのではなく,題材に基づいて自分の意見を書くとことの難しさを学んだようです。
« 2007年01月 | メイン | 2007年03月 »
2月初旬から始めた小論文講座の第3回目の様子です。

要約練習も終わり,いよいよ小論文という回になって,大流行の風邪(インフルエンザ)のためか欠席者が多く見られました。しかし,参加者は頑張っていました!!自分の好きなことだけを書くのではなく,題材に基づいて自分の意見を書くとことの難しさを学んだようです。
第49回高等学校卒業式が行われました。
50期生高校2年生は中学1年生から高校2年生までの代表としてこの式に参加しました。
49期生は33名もの3年間皆勤者と、その中には14名もの6年間皆勤者がいました。
49期生高校3年生は何事にもまじめに取り組む姿勢が常にあらわれる学年でした。これからは50期生が最高学年になります。来年の今日、この卒業式を誇り高い気持ちで迎えられるよう、一年を全力で走ってほしいと思っています。
2月17日(土)昼から中学棟,視聴覚教室で社会科研究発表会が行われました。
高校2年生は,文Ⅱの特講日本史の授業から3グループ,特講世界史からは2グループ,国際科留学コースからは1グループが発表を行いました。
日本史:「頭髪と化粧の歴史」 「ファッション」 「真田幸村」
世界史:「クレオパトラ」 「アールヌーボー」
国際科:「比較文化~オーストラリア~」【1年留学から帰国して】
授業で発表した中から選ばれた5グループです。高校二年生らしいしっかりした発表になりました。
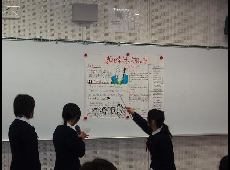



Q:「入ってよかったと思うことは何ですか?」
A:
③入ってよかったと思うことの続きからです
ⅲ.先生
SFCがすごいことの一つとして、教授たちと学生とのキョリがこんなに近い大学は、なかなかないでしょう。普通の大学では、なかなかエライ先生と普通の学生が一対一でゆっくり話を聞いてもらうなんてことはないらしいですが、
SFCでは、メールでアポさえとれば、ほとんどの先生たちはゆっくり話を聞いてくれるはず。また、SFCの先生たちは、「誰も考えたことがないこと」を言ってくれる学生が好き。分かったふりをしたり、無難なこと言ったりするよりも、積極的に質問したり、突拍子もないことを考える人のほうが求められているのです。
教授たちもすごい個性的な人々が多い。みんな学生よりも熱いパッションを持ってますね。従来の教育とは違った、新しい視点での教育を目指している人たちなのです。
世界的にも有名な人は、村井純さん(インターネットの父)、佐藤正彦さん(だんご兄弟の生みの親)、元大蔵大臣の竹中平蔵さんもSFCに復帰するらしいです。雑誌やTVに取り上げられるような先生たちも多くて、素晴らしい教授陣だなぁーっとつくづく思います。
ⅳ.SFCの場所
SFCは、その名のとおり湘南藤沢にあります。実際に写真で見たら分かるとおり、山の中にあって、とーーーーってものどかな場所にあります。夜景がめっちゃキレイです。夏になると、くさい牛のにおいがします。
最先端なことを勉強する大学ゆえに、このロケーションのギャップには、逆に良いバランスを保っていると思います。僕はオープンキャンパスで初めてこの地に訪れて、なんていいところなんだろうって感動した覚えがあります。写真を添付するので、ぜひそちらで見てみてください。
④最後に
SFCという大学はほんとに特別な場所なんだなぁって思います。それと同時に、何事においても基本的には「自由」なのです。(SFC=自由)
しかしこの自由とは、つまり全てが自分次第という意味です。
僕は高校生の時、やりたいことが見つけられずにいました。
だからSFCという、ある意味「どうにでもなる」大学を選んだのも一つの理由です。
ただし、SFCがどうにでもなる大学であることはたしかですが、それをどうにかするのは自分自身の力です。
僕自身、SFCに入学する努力よりも、入学してからの努力の方が何倍も何十倍も勝っています。
法学部、建築学部、経済学部、工学部などは、カリキュラムがもう決められていますが、SFCの総合政策学部、環境情報学部にはそれはありません。
そのような環境におかれたとき、自分で自分の将来を見つめて、自分の道すじを立て、その道を突っ走る勇気があるかどうかだと思います。
それを認識できない人たちは、全て学校まかせで、最後には失敗します。SFCで失敗する人も少なくはないでしょう。
SFCという環境を、日本一の最高の環境にできるかどうかは、全て自分の力次第だということを、是非心にしまっておいてほしいです。
前回に引き続き慶応大学からのレポートです。
Q:「入ってよかったと思うことは何ですか?」
A:
③入ってよかったと思うこと
入ってよかったなぁ~っというか、SFCって自分に合うなぁ~って思うことはよくあります。主に次の4つですね。
ⅰ.文理融合型教育
言ったとおり、SFCには理系と文系の人が混在していて、授業自体も、SFCにいる限り、総合系も環境系も両方学べます! こんな大学、日本の中で他にめったにありません。とても特殊です。 SFC内の人間関係の中で、誰が総合政策学部で、誰が環境情報学部かというのも正直わかりません。
僕が高2のちょうど今頃のことです。僕は理系か文系かどっちの進路か迷って、担任に相談した覚えがあります。なんで理系か文系か選ばないといけないんだろうってすごい悩みました。僕自身、どっちのタイプかはっきりしなかったし、どっちの科目もバランスよかったけど、これっていう得意科目もなかったんですね。何より、自分が大学で何を勉強したいか曖昧だった。
あと、これは僕が今でも持っている勝手な持論なんですけど、自分っていう人間を成長していく中で、いろんな分野の知識は、全て一つにつながっていると思っていました。 よく、文系は数学が必要ないとか、理系は国語が必要ないとか消去方的に言う人がいるけど、それはちょっとおかしい。 だんだん、この国の受験制度とか受験勉強、理系か文系か無理やり分けさせられる体制が、すごくうんざりでした。
だから、慶応SFCの説明会で、「SFCには文理融合というコンセプトがある」「文系、理系かは関係ない」という事を聞き、 僕は、「ここしかない」と思うようになりました。この大学に入ってみて、やはり思ったとおりだ!!ここは自分に適した場所なんだ!!って実感しました。
ただし、全ての人に対してこのような場が適しているとは限りません。法律を真剣に学びたいのであれば、ちゃんとした「法学部」に進んだ方がいいでしょう。建築ならば建築学部、経済ならば経済学部に行けばいいと思います。デザインだけをただ単にやりたいなら、デザインの専門学校に行けばいいんです。
要するに、どのような視点で法律を習うのか、どのような方法で建築に取り組むのかが重要だと思います。誰もやったことのない視点で取り組みたい!自分のやりたいことは決まっているけど、別の分野からのアプローチをしたい!っていう人には、こんなに適した環境はありません。残念ながら、僕の周りにも結構いますが、「SFCは何を学んでも中途半端!」と愚痴ってる人もいることも事実です。
ⅱ.学生
SFCには、個性豊かな人が多くいるとよく言われます。そもそも、慶応の学生というある種のブランドよりも、SFCの学生だというプライドのもってたりします。ⅰ.で言ったように、文系、理系さまざまな人がいるだけでなく、帰国子女の割合も高く、一般入試だけでなく、AO入試などにも力を入れていれています。特技を持っている人も比較的多いです。しかも、この大学で生活していく中で、その特技をさらに一つ、二つ増やしていこうとする人が多いですね。
SFCには、「ダブルメジャー」というコンセプトがあります。全然違う分野で、二つ以上自分の武器となる得意分野を育てたいんでしょうね。僕の周りの友達も、割と幅広い分野の人たちが多いです。SFCに来たからこその友達ですね。ホントに素晴らしい人たちに出会えたなぁーって思います。
ⅲⅣは次回へ
1月24日(水)HRで松石先生から慶応高大連携講座について話がありましたが,実際の様子も知りたいと思い,第1回慶応高大連携講座からSFCに入学した47期生(現在3回生)の福島くんに協力してもらうことになりました。
以下「A」の内容は福島くんからのメール(一部省略させてもらっています)を掲載します。
スタート!!
慶応SFCでの生活について、僕が今高2のみなさんに教えてあげられることを報告しますね。ぜひ参考にしてみてください。
Q:環境情報学部でどんなことをしているの?
A:
①環境情報学部で専攻していること。
僕はいまSFCで、稲陰正彦先生の研究室(imgl)にお世話になっています。稲陰研究室は、SFCの中のKeio Media Designというグループに属していて、主にデジタル・エンタテイメントコンテンツをつくっています。
具体的にいうと、映像や3Dグラフィックス、音楽などのメディアを作って、新しい、次世代のコンテンツ(作品)を作っています!!!今話題の、「ユビキタスコンテンツ」というやつですね。
研究室の中にも、たくさんのグループが活動していますが、僕らのグループは、あのケイタイで有名なKDDIと一緒に、原宿のスタジオで、今年5月から長期展示するためのコンテンツ(作品みたいなもん)を、去年から一年がかりで製作している最中です。
うまくこのコンテンツが完成した後は、いくつかの学会に論文を発表するつもりです。もしかしたら、オーストリアや、アメリカのサンディエゴあたりに飛んで、世界のクリエイターやアーティストたちと一緒に展示できるかもしれません☆
とまぁ、こんな感じですね。うまく説明できたかな?? デザイン、音楽、映像、プログラミング系なので、簡単にいうと、がっつりパソコン系ですね!自分で作曲したり、映像を作ったり、それらを使って新しい表現の場、空間を作ってみたい!っていうのが僕個人のテーマです。 ただし、毎日毎日むちゃくちゃ忙しい!!やること多すぎ!! まぁとっても楽しいし、やりがいがあるので充実した日々を過ごしています!
Q:高大連携講座はディベートをしたり小論文を書くと聞いたけれど,文系の人が行くの?でも,大学の案内は理系と文系両方あったのだけど。
A:
②連携講座で行くと、高校で理系文系関係ないか。
連携講座で行くか行かないかにかかわらず、SFCという教育環境の中で、高校のとき理系か文系かというのは、ほぼ関係ないと言っていいでしょう。
高校で文系だった人も環境情報学部にいるし、理系の人でも総合政策にいたりします。僕の周りの人には、自分は文系だったけどとりあえず両方の学部を受験してみたら、環境情報が合格したから環境情報に来たっていう人もいます。
僕が連携講座を受けたとき、なんで環境情報学部にしたかっていうと、「なんとなく」です。これは、僕が高校の時、理系と文系どっちにしようか迷ったときと同じで、理系だったら、文系の分野にも手を出せると思ったからです。
ただ、重要なのは、来年度からSFCのカリキュラムは大幅に変更すること!! どうやら来年度からは、総合政策学部はかなり文系に偏るみたいで、(法律、国際政治、コミュニケーション、言語系、ビジネス系など)、環境情報学部は、かなりの理系に偏るらしいです。(プログラミング、バイオテクノロジー、心理系、メディアデザイン系、建築系など)
また、僕らの学年までは総合系、環境系に加え、複合系というのもあったのですが、来期からは複合系がなくなるようです。さらに、以前は環境学部にいる人が総合系科目をとったり、総合学部にいる人が環境系科目をとっても、卒業単位を取得できたのですが、来期からは、授業を受けることができたとしても、卒業単位はくれないみたいです。
よって、来年度からは、理系なら環境、文系なら総合のような構図がいっそう強くなるかも…。ただ、理系なら環境に行かないといけない!!みたいな強制ではないので、そこは自分次第ですね。
2月3日(土),4日(日) 「センター試験早期対策模試」が行われました。
2007年の年明けとともに,個々の大学受験にむけての意識が高まりつつあります。
3日(土)は授業が終わった後,数学と理科。理科2科目の生徒は17:50終了。
翌4日(日)は英語,国語,社会8:45~16:20。その間に漢字検定も受検する生徒が40人。
ハードスケジュールに少々ばて気味かもしれません。
1月24日(水)HRでの「AO・慶応高大連携講座説明会」を受けて,学年で「AO・小論文対策講座」を開講することになりました。
木曜日放課後16:50~17:20です。42名の申込者があり,他の日程に変更してもらう人がでるほどでした。
第1回目は、「要旨」をまとめるにいたるまで、段階をふんだ「練習」と、「意見(感想)」でした。
教室では3人の担当教員が巡回し、個々にアドバイスを与えていきました。
90分間の集中した時間を送ることができたようです。
文章上達には時間がかかりますが努力してほしいと願っています。