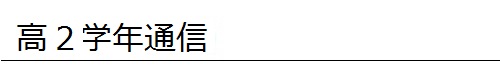教育経済学
近年「教育経済学」が注目されています。子どもへの効果的な教育方法を探るにあたり、教育における統計的なエビデンス(証拠・根拠)を用いるというものです。収集したデータを分析し、社会の構造を明らかにすることで実証的に分析することを目的としたものになります。
教育経済学の書籍は多く出版されていますが、中でも興味深かった2つの事象を紹介します。
①親が「勉強するように言う」ことは逆効果
親の関わり方がどの手渡子どもの学習時間の増加に貢献しているのかという研究結果からこの行動の効果のなさが立証されました。「勉強するように言う」のは親としても簡単なことなのですが、この声かけの効果は低く、ときには逆効果になるようです。親としてもエネルギーの無駄遣いになってしまうのでやめたほうがよさそうです。小学校低学年の場合は、「勉強を見ている」または「勉強する時間を決めて守らせている」という行動はかなり効果が高いようですが、高校3年生に対しては「見守る」「応援する」という形がベストだと感じます。

(『ドラえもん』https://www.pinterest.jp/pin/178666310198097393/より引用)
②友達が与える影響
高校や大学の卒業式で「よい友人に恵まれて、素晴らしい時間を過ごすことができた」という感謝の言葉が聞かれることが多いものです。それに比べると「よい先生に恵まれて」という言葉が前者の言葉ほど聞こえてこないのは、高校生にとって友人は教員よりもはるかに強く影響を受ける存在だからなのでしょう。友人や周囲から受ける影響のことを、よいものも悪いものも、経済学では「ピア・エフェクト」と呼びます。アメリカや欧州6カ国、チリ、中国などで行われた研究では周囲の子どもの学力が高くなると子どもたちの学力の変化にどのような因果効果を持つのかが明らかにされています。結論は、「学力の高い友達の中にいると、自分の学力にもプラスの影響がある」というものでした。「受験は団体戦」という格言はこれらの研究で信憑性の高いものであることが分かるかもしれません。