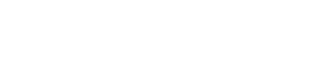学園ブログ
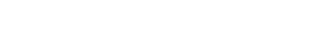
- ホーム
- IT時代を生き抜く
IT時代を生き抜く
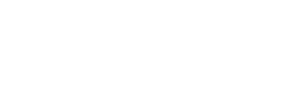
2018年09月26日
プログラミング教育

当初、文部科学省はプログラミング教育とはプログラミング的思考を育てることで、コーディング(プログラム言語を用いてプログラムを書いていくこと)をすることではないと言っていました。順序立てられた論理的思考ができれば良いとしていたのです。ところが、ふたを開けてみると、「児童がプログラミングに取り組んだり、コンピュータを活用したりすることの楽しさや面白さ、ものごとを成し遂げたという達成感を味わうことが重要です。」と書かれています。ということは、実際にコンピュータに触れなければならない。さらには(コーディングではないにしろ)プログラミングをしなくてはならないのです。
プログラミング的思考を養う教育は、理科や算数では従来からしてきましたし、ちょっとした工夫でまだまだ増やすこともできます。しかし、実際にコンピュータに触れプログラミングを行うとなると、もうほとんど別の授業です。算数で行うにしても、コンピュータに触れるとなると、パソコンのある教室へ行かなくてはなりません。幸い、本校ではタブレットを導入していたので、教室で行うことができました。(どんな授業をしたのかは、昨年度2月のブログをご覧ください。)
プログラミングをしてトライアンドエラーを繰り返すことにより、プログラミング的思考を学ぶことができます。2017年度に授業を開始し、2018年度は全教員でプログラミング教育に向けどんな授業ができるか考えていきます。2020年度から始まるプログラミング教育に先駆けて、全校をあげてプログラミング教育に取り組んでいきます。
(小学校教諭 隅田心吾)