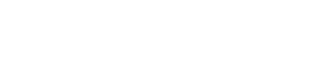学園ブログ
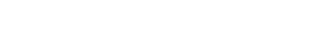
- ホーム
- 親孝行・やってみなはれ
親孝行・やってみなはれ
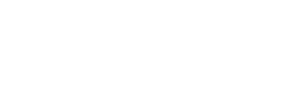
2019年03月01日
一・九の十、二・八の十の話

いちくのじゅう、にはちのじゅうと読みます。
私の剣道の先生が指導されるときの心得としてよくおっしゃっていました。
剣道指導において指導される側は子供から大人まで様々なレベルの方がいらっしゃいます。
初心者から高段者まで技量は全く違いますがどのような心持で指導に臨むかということを説いた話でした。師は武道を志す者が集う、京都の武道専門学校で学ばれ、剣道指導者としての道を歩まれました。おそらく、その時に指導者の心得として学ばれたことだと思われます。 師は子どもを指導するのはある程度技量を持った有段者を指導するよりはるかに疲れる、とよくおっしゃっていました。
師は子どもを指導するのはある程度技量を持った有段者を指導するよりはるかに疲れる、とよくおっしゃっていました。
「稽古においては持っているものすべてを出しきらねばならない、指導者は指導を受けるものがすべてを出せるように導かねばならない、そのためには相手が一の力しかないのであればこちらが九の力を出し、子弟合作で十の稽古にするのが指導者である。二の場合は八の力を指導者は出さねばならない、だから指導者が大きな力を出さねばならない子どもの指導は大変疲れるのだ、相手の技量が低いからといって指導者がいい加減に扱い済ませる稽古はいけない稽古だよ。」と言っておられました。
この話は初心のものほど丁寧に力を注いで指導せよ、技量が低いからと言っていい加減な指導はするな、初心の者であってもその良さを引き出すことを絶えず考え、力を抜いたり、いい加減な指導をしてはいけない、むしろ上手を指導するよりも手厚い指導をせよ、という教えでしょう。
子どもたちに接するものとして、心しておかねばならない教えとして大事にしています。
(小学校副校長 成地 勉)