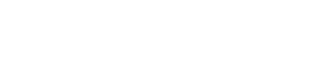学園ブログ
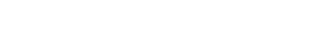
- ホーム
- 学園自然百景
学園自然百景
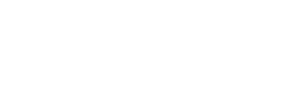
2025年01月24日
146.「ドングリのせいくらべ」
~雲雀丘学園小学校教諭 天井比呂~

この言葉は、可愛らしいドングリを使った言葉ではありますが、否定的な言葉として使われます。「五十歩百歩」「大同小異」などと同じような意味になります。どれもこれも大差がないということでしょう。
しかし、これは一つの樹木の中での話になります。ドングリと一言でいってもいろいろな種類があり、大きさも随分違います。クヌギの丸い大きなものから、ウバメガシのように小さめなもの、スダジイのように色の黒っぽいものマテバシイのように細長く大きなものと様々です。コナラと聞くと、小さいドングリのように思いますが、しっかりとした大きめの代表的な形のドングリです。
学園にはコナラ、アラカシ、シラカシ、マテバシイなどがありますが、子どもたちや保護者の方たちと池のかいぼりを行った時に、ゲストティーチャーのYさんが、「池の淵のアラカシのドングリがとても大きいのですが、種類が違うのでしょうか。」と仰ってこられました。見ると、その方のアクセサリーにしておられた標準的なものに比べるとかなり大きいのです。里の上にある線路脇のアラカシなどの実を見ると確かに池のドングリよりも小さいのです。池のアラカシは、よく見ると、根元でエノキと交わった感じになっていてその影響かなとも思ったのですが、私見ですがどうも生育環境の違いのような気がします。池の淵のアラカシは、池が下にあるため、水分をはじめ、かなり肥沃な場所に思えます。一方、線路脇のアラカシは、やや乾いた地面の砂が含まれた土壌です。これが一般にあるアラカシの土壌のような気がします。
土壌が違えば同じ種類の樹木でもその実はこれだけ違うのでしょう。人の手は入らなくてもです。人も同じことがいえるでしょう。土壌が人を育てる。土壌は、家庭であり、学校である生活基盤と言えるでしょう。
ただ、アラカシにとっては土壌基盤だけでなく、そこには日照や気温などがかかわり、外的な要素もあるでしょう。それは、人にとっては教育にあたるのではないでしょうか。
「ドングリの背比べ」は、教育への警鐘なのかもしれません。個性を伸ばすには教育が大切だぞという。