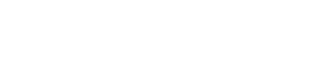学園ブログ
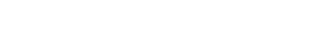
- ホーム
- 学園自然百景
学園自然百景
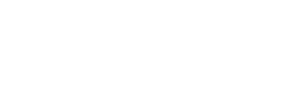
2022年09月02日
33.「誤解を解きたい」
~雲雀丘学園小学校教諭 天井比呂~


早乙女花
赤紫の花芯がお灸のあとに似ているということから、ヤイトバナという別名もあります。
ところが、和名としてあるのは、ヘクソカズラという名前です。なんとも言えない名前です。これは、葉や茎を折ったり揉んだりするとその名前に納得してしまう匂いがします。
よく聞くドクダミという名前も匂いの特徴から名前がついたという説があります。
植物の名前は、その特徴から人間が感じた名前を付けることがよくあります。このヘクソカズラの名前は、万葉集に出てきます。
「皂莢(そうきょう)に延(は)ひおほよれる屎葛(くそかずら)絶ゆることなく宮仕えせむ」
この詩は、「皂莢」というとげのある植物に巻き付いて伸びる「ヘクソカズラ」に自分をたとえて、宮仕えする決意をのべたようです。つまりこの名前は、奈良時代にはすでについており、存在していたということになります。

ひばりの里のフジにまきつくヘクソカズラ
名前は、もちろん私たちに植物の特色を教えてくれるのですが、その名前で誤解しないように植物についてよく知らなければなりません。