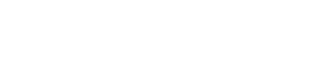学園ブログ
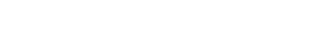
- ホーム
- 学園自然百景
学園自然百景
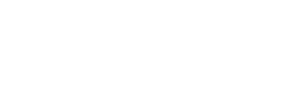
2022年12月16日
47.「藁をもすがる」
~雲雀丘学園小学校教諭 天井比呂~

頼りにならないものとしてたとえられるのが、藁です。空洞で、一本では、すぐに折れてしまうからでしょうか。確かに「溺れる者」は、浮いている一本の藁でもつかんでしまうでしょう。もちろん役に立たず、頑丈な板や空のペットボトルをつかんだ方が、命は助かるでしょう。藁とはいったいなんなのでしょう。もともとは、漢字の成り立ちからすると、立ち枯れた植物をあらわすようです。枯れた植物を想像すると、確かに弱い感じがしますが、本当にそうなのでしょうか。藁の中で私達と関係が深いのは、麦藁や稲藁です。麦わらは、麦藁帽子がなじみ深いでしょう。では、稲藁は、というと、思いつかない場合も多いのではないでしょうか。
学園では、子どもたちが代掻き、田植え、観察、稲刈り、はざがけ、脱穀までの作業を通して経験し、稲藁を使って、しめ縄を作ります。お正月を迎える為のしめ縄は、稲藁を使用します。
自然百景からは、離れてしまっているようですが、この稲藁が、自然の生き物に頼られる存在になるのです。それが、次の写真です。


無造作に投げ入れられた藁の束。稲刈りが終わり、池底に溜まったヘドロ(落ち葉や藻が、沈んで腐ったもの)を児童や保護者の協力の下きれいにし、すんでいた生き物たちを一度救出します。


綺麗になったあと、再び戻し、そのあとに稲藁の束を投げ込みます。ここが、この生き物たちの冬越しの場となるわけです。春になると、この稲藁の中に産卵し、沢山の生き物があらわれます。池などが、凍ると全滅したのではないかと心配するのですが、この稲藁が、命を救うのです。
もちろん稲藁は、これまで、その空洞の茎、加工のしやすさを活かして、わら靴やわら草履、編み笠や敷物などさまざまなものに役立てててこられました、使わなかった藁や籾殻は、来年の為の田んぼの肥料としてすきこまれます。
全く捨てるところがない、無駄なところがないまさに「もったいない」を人々はこの藁を利用し続けたわけです。いま、農家での稲藁の野焼きが禁止されるところも多くその処理に困っているところもあるようです。なんとか、この藁を有効活用できる方法が見つかればよいなと思います。「藁をもすがれる」ことを願います。