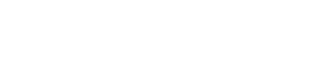学園ブログ
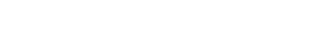
- ホーム
- 学園自然百景
学園自然百景
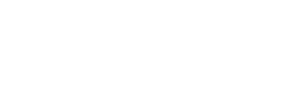
2023年05月19日
66.「堅く信じる」
~雲雀丘学園小学校教諭 天井比呂~

こどもの日には、ちまきを食べた子どもたちも多いことでしょう。ちまきを食べる風習は関西が主流で関東では柏餅を食べる風習であったとも、言われています。
ちまきは、茅の葉でもち米を巻いて蒸したり煮たりしたことからちまきと呼ばれるようになったそうです。今では笹の葉でもち米で作った少し甘い餅を巻いているのがよくこどもの日に食べられています。
小さい頃、このちまきを食べるときにそれを巻いて縛っていた紐を外すのに苦労していた思いがあります。あの紐のような植物の茎のようなものをあまり気にしていなかったのですが、調べて見ると、イ(イグサ)であることがわかりました。中華ちまきとよばれるものは、タコ糸で結んであることが多いですが、端午ノ節句に食べるちまきは、イ(イグサ)が多いようです。あの畳の原料となるイグサです。

ひばりの里の「イ(イグサ)」全景
4月28日

イ(イグサ)の花の出穂
5月1日

イ(イグサ)の花 1

イ(イグサ)の花 2

イグサの花の拡大 花びららしきものが見えます。
今、ひばりの里ではイの花の花盛りです。とはいっても色鮮やかなわけではありません。とても小さく、6枚の花びらもあるのですがはっきりとわかるものではありません。ただ、イは、写真のように扇のように広がり、花が星を散りばめられたように見えます。
イの花は、茎の途中に咲いているように見えますが、花の咲いているところまでが花の茎で、その先は苞と呼ばれる葉が変化したものです。茎は地下に這っており、葉は、退化したようになっているようです。少し変わった植物といえます。
イは、弥生時代の遺跡からも敷物のような形で出土しているようで、人間に随分昔から利用されて来たようです。その後、むしろやござ、畳と歴史とともに進化し日本独特の文化を生み出したといえます。また、燈心草(トウシンソウ)とも呼ばれその芯の部分をロウソクの芯としても利用されていたようです。
真っ直ぐ伸びた花茎と苞が集まっていることからついた花言葉だと言われます。子どもたちの未来が明るい未来だと堅く信じたいものです。