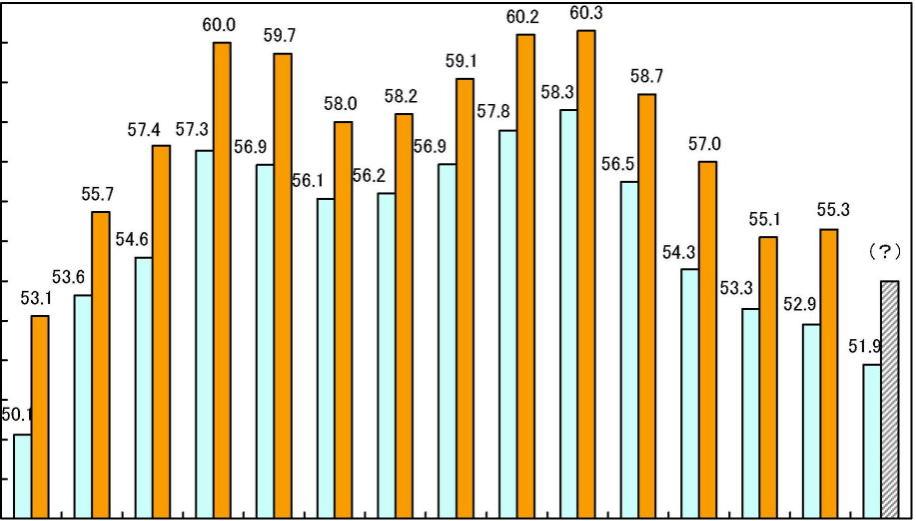ちょっとした話
昨日、11年前に卒業した卒業生(私が初めて担任を持った学年です。)が学校に訪れました。彼は、本校を卒業し、国公立大学に入学し、その卒業後、大学院に行っていたそうですが、10年以上音沙汰がなく、本当に久しぶりでした。今回、訪れた理由は、留学するそうで、英文の卒業証明書と成績証明書を取りに来たのです。元気そうで何よりと思いました。今年は、懐かしい卒業生に会う年ですね。実は、同じ11年前の卒業生に文化祭の時にも会ったのです。本人は、久しぶりに母校に遊びに来たそうなのですが、この学年の生徒に会うのは、ここ数年来です。2回も会うとは、すごい偶然だと思います。しかも、高3で私のクラスの生徒ばかりとは驚きでした。
ところで、話は変わりますが、最近の子供はコンピューター(ゲーム)ばかりやっていませんか。携帯やコンピューターがこれだけ普及した時代なので、仕方がないかも知れませんが、昔ながらの遊びを少し思い出す今日このごろです。少し前に数楽パズルをいくつか紹介しましたが、今回は、紙と鉛筆さえあればちょっとしたときに遊べるものを紹介しておきましょう。3ます×3ます(4ます×4ます)の方眼を書きます。そこに順番に○と×をつけていくゲームで、一直線に並べば勝ちとなるものです。やったことはありませんか。ほとんど勝負はつきませんので、これを発展させましょう。正方形を線で書き、対角線を引き、さらに、真ん中に縦と横の線を書きます。(つまり、合計8本の線を書きます。)そうすると、線の交わりに9個の点が出来ます。その9個の点に駒を置いていきましょう。(駒は、白と黒を3個ずつ用意しましょう。)順番に置いていき、3個が一直線に並んだら勝ちです。ただし、全部で6個置き終えたら、次に線に沿って一個ずつ移動していくのです。ただし、駒を飛び越えることは出来ません。また、同じ動きが3回続くと、引き分けで終わりです。やってみてください。
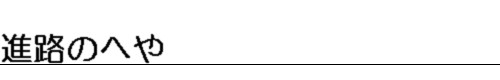
 こんにちは!46期生のA.H.です。
こんにちは!46期生のA.H.です。 文章を図やグラフで表現するということは大切だ。何を問われているのか,問題の内容把握の手段としても大切だと思う。これができている答案とできていない答案では,明らかに出来具合に差がある。
文章を図やグラフで表現するということは大切だ。何を問われているのか,問題の内容把握の手段としても大切だと思う。これができている答案とできていない答案では,明らかに出来具合に差がある。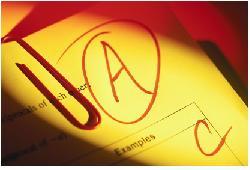 ともかく、今年も、「おお、こんな勘違いをする人がいるんだ、これは、この部分は理解しているわけだから、半分くらいの点はあげよう」とか「ううむ、ここまでわかっていないのは、受けた教育が悪いんだろうなあ。どこまで部分点をあげたものか・・」などと延々と議論しながら採点基準を決めて点をつけました。ともかく、まちがい方のパターンというのは、われわれ出題者(というか、プロの物理屋)の想像をまったく越えてバラエティーに富んでいます。個別のまちがえた答案に直に接してみて、どこでどのように混乱して、どうまちがえたかを考えて、汲み取るべきものを汲み取っていくのが、採点でしょう。
ともかく、今年も、「おお、こんな勘違いをする人がいるんだ、これは、この部分は理解しているわけだから、半分くらいの点はあげよう」とか「ううむ、ここまでわかっていないのは、受けた教育が悪いんだろうなあ。どこまで部分点をあげたものか・・」などと延々と議論しながら採点基準を決めて点をつけました。ともかく、まちがい方のパターンというのは、われわれ出題者(というか、プロの物理屋)の想像をまったく越えてバラエティーに富んでいます。個別のまちがえた答案に直に接してみて、どこでどのように混乱して、どうまちがえたかを考えて、汲み取るべきものを汲み取っていくのが、採点でしょう。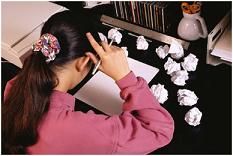 まず,問題作成には,大学入試センターから任命され委員となった大学教授でつくる「教科科目第一委員会」があたる(構成人数は640名以内と定められている。任期は2年。試験教科に応じて24部会に別れている)。この人選については,大学入試センターが文科省から委嘱されており,イギリス人,アメリカ人を含めて全国国立大学から極秘に選ばれる。数学の作問委員会はメンバーが14人で毎年半数ずつが入れ替わる。
まず,問題作成には,大学入試センターから任命され委員となった大学教授でつくる「教科科目第一委員会」があたる(構成人数は640名以内と定められている。任期は2年。試験教科に応じて24部会に別れている)。この人選については,大学入試センターが文科省から委嘱されており,イギリス人,アメリカ人を含めて全国国立大学から極秘に選ばれる。数学の作問委員会はメンバーが14人で毎年半数ずつが入れ替わる。 大学入試センターは,現行のセンター試験「地理歴史」と「公民」のそれぞれの試験枠を同一枠に統合し,“地歴2科目選択”を可能とする時間割の改編案をまとめ,本年度内に告示する予定のようだ。早ければ22 年度(現高1)からの実施も考えられる。
大学入試センターは,現行のセンター試験「地理歴史」と「公民」のそれぞれの試験枠を同一枠に統合し,“地歴2科目選択”を可能とする時間割の改編案をまとめ,本年度内に告示する予定のようだ。早ければ22 年度(現高1)からの実施も考えられる。
 センター試験まで100日を切り,また,私大の公募制推薦入試の願書受付も始まるなど,20年度入試に向けて,受験者・大学双方ともに本格的な動きが目立ってきた。この辺りで,来年度入試を予測してみようと思う。
センター試験まで100日を切り,また,私大の公募制推薦入試の願書受付も始まるなど,20年度入試に向けて,受験者・大学双方ともに本格的な動きが目立ってきた。この辺りで,来年度入試を予測してみようと思う。