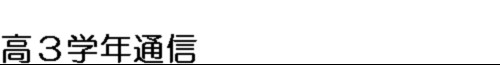選特化学 授業の補足16

無機化学を扱っています。周期表を左から右へ順番に説明していき、今日は15族である窒素が出てきました。空気中の窒素N2は安定ですが、自動車のエンジンでは高温高圧なので、一酸化窒素NOなどの窒素酸化物が発生します。一酸化窒素は大気中で二酸化窒素NO2を経て、硝酸HNO3に変わり、酸性雨として被害をもたらします。
ガソリンエンジンから排出される排気ガスには、大気汚染物質として、一酸化炭素CO,炭化水素CmHn,窒素酸化物NOxが含まれています。最初の2つはガソリンの不完全燃焼によって生じ、NOxは空気中のN2とO2によって生じます。ガソリン車では排気管に仕込まれた触媒(白金Pt,パラジウムPd,ロジウムRhなど)によって分解され、8割以上が除かれています。このうち、NOxはRh触媒によってCOと反応し、N2とCO2に変化します。
一方、ディーゼルエンジンの場合、圧縮比が大きく、燃料がシリンダー内で完全燃焼するため、不完全燃焼によって生じるCOやCmHnはほとんど発生せず、NOxの発生量が多いのが特徴です。Rh触媒でNOxを除去するには還元剤であるCOが必要ですが、ディーゼルエンジンの排気ガスにはほとんど含まれず、従来のディーゼルエンジンでは多量のNOxが排出されていました。近年は尿素(NH2)2COを添加し、分解によって生じるアンモニアNH3を利用することで排気ガスの問題が解決し、ふたたび燃費のよいディーゼル車が見直されるようになりました。