
文系に出している課題についてです。テーマが重いこともありますが、立場の違いによってさまざまな意見があり、どれが正解とは言えません。患者,患者の家族,医療者のそれぞれが自らの経験を元に正しいと信じていることを主張しているのですから、それを踏まえて自分の意見をまとめて欲しいと思います。新書を5冊以上読むように指示していますが、どこまで進んでいますか。iPS細胞から精子を作り、体外受精させることがマウスとはいえ現実に可能になっている以上、文系だから知らないではすまされないと考えています。
臓器移植
脳死と臓器移植法
中島みち 文春新書140
私の臓器はだれのものですか
生駒孝彰 生活人新書033
腎臓放浪記 臓器移植者からみた「いのち」のかたち
澤井繁男 平凡社新書300
臓器移植をどう考えるか 移植医が語る本音と現状
秋山暢夫 講談社ブルーバックスB-900
脳死・臓器移植の本当の話
小松美彦 PHP新書299
先端医療のルール 人体利用はどこまで許されるのか
橳島次郎 講談社現代新書1581
生体肝移植 京大チームの挑戦
後藤正治 岩波新書新赤版804
臓器は「商品」か 移植される心
出口顯 講談社現代新書1549
生殖医療
生殖医療のすべて
堤治 丸善ライブラリー285
不妊治療は日本人を幸せにするか
小西宏 講談社現代新書1602
代理出産 生殖ビジネスと命の尊厳
大野和基 集英社新書0492B
生殖革命
石原理 ちくま新書170
生殖革命と人権 産むことに自由はあるのか
金城清子 中公新書1288
生命観を問いなおす エコロジーから脳死まで
森岡正博 ちくま新書012
生殖医療と家族のかたち
石原理 平凡社新書531
遺伝子医療への警鐘
柳澤桂子 岩波現代文庫学術83
終末医療
「尊厳死」に尊厳はあるか ある呼吸器外し事件から
中島みち 岩波新書新赤版1092
患者革命 納得の医療納得の死
中島みち 岩波アクティブ新書6
リビング・ウィルと尊厳死
福本博文 集英社新書0131B
終末期医療はいま 豊かな社会の生と死
額田勲 ちくま新書031
安楽死と尊厳死 医療の中の生と死
保阪正康 講談社現代新書1141
安楽死のできる国
三井美奈 新潮新書025
脳死・クローン・遺伝子治療 バイオエシックスの練習問題
加藤尚武 PHP新書086
死にゆく人のための医療
森岡恭彦 生活人新書090

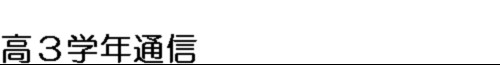















































 ABO式血液型の遺伝について説明したので、凝集反応についても併せて説明しました。
ABO式血液型の遺伝について説明したので、凝集反応についても併せて説明しました。










