国連高校生セミナーに参加した二人目の生徒のReportです。セミナーの中で聴いた内容,今までの経験から感じたことなどたくさん盛り込んでくれました。伝えたいことを整理してくれると、分かりやすい文章になると思います。これからも情報発信する経験は必要ですね。
I participated in the United Nations environmental seminar sponsored by JICA Hyogo on Saturday, March 19, 2011. First of all, in the seminar room, Associate Professor Hiroaki Ishii at Kobe University lectured on a basic environment. Then, I was able to listen to a lot. To worldwide, until the present age, more than 56% and halves of the cause of Global warming is combustion of fossil fuels. 50% or 36~45% of carbon is stored in the forest in the terrestrial ecosystem. If we can make CO2 more than carbon, plants can not only to do photosynthesis but can store CO2 through combining O2 with carbon in air into CO2 even under the circumstances of the deforestation. It should be the only material that can be manufactured from the CO2 exhaust seeing overall because the amount of the CO2 exhaust is also the fewest in the forest, and forests absorb and use the amount of 5~10 times the exhausted CO2 compared with the ratio of wood, iron, and aluminum; 1:191:791.
I was able to learn a lot. After the lecture, we made a group and had a time to discuss. A theme: “Isn't there any better method to take CO2 into trees by using trees?" was given by a native speaker. Our group made a conclusion that "The number of wooden buildings should be increased." After that, a different title “what should you do to stop Global warming?” was discussed. With the other party group, I was able to know the different aspect from our group. As our fundamental opinion, Do not start to stop Global warming if one man one who first does it doesn't consider Global warming.
It was the one. A concrete method to hold off Global warming was devised. When being possible to talk by the group with a quite different idea like directionality and the aspect, etc. it became a very important chance. I was able to have the expectation of the risked palanquin..person with a different opinion.. ..We can find the solution by talking...The above is a part of what I felt through this experience.
And, it is a technology to being able to speak English first of all with native's people necessary for us. The other party group was an international department, and we had a hard time considerably only because we caught English this time. More..school..English..work..strengthen..slow..feelings..other party..tell.And, we who participated in this event are now.Do : the experience of this time even by oneself.It was felt that it was strong when a lot telling it. I thought that they had to act to achieve. T.K.


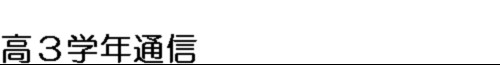

















































































































































































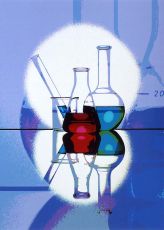


















































 ABO式血液型の遺伝について説明したので、凝集反応についても併せて説明しました。
ABO式血液型の遺伝について説明したので、凝集反応についても併せて説明しました。
































































































